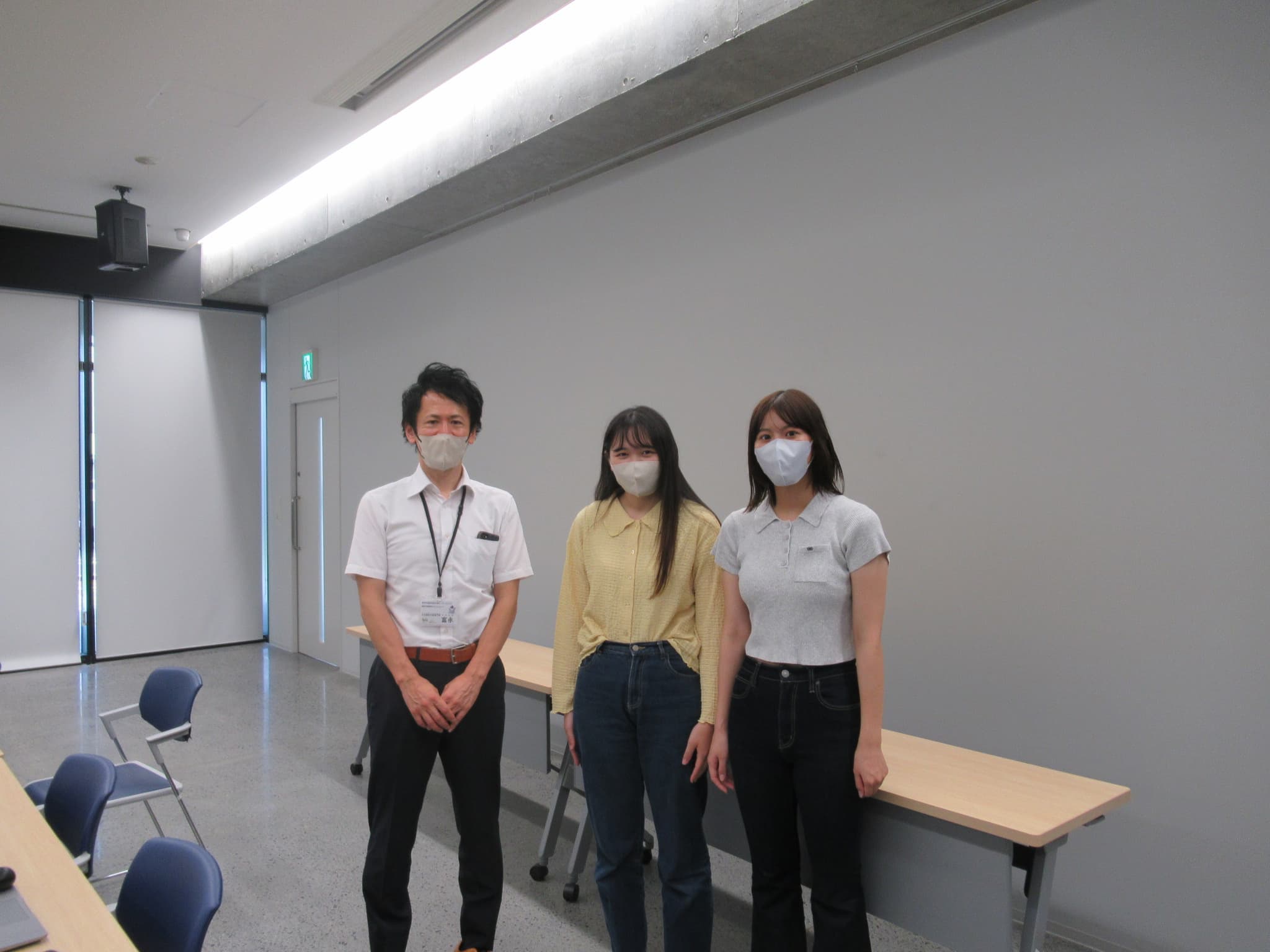障害者福祉のPRと人材確保
事業概要
| 連携自治体 | 事業名 | 主な担当教員 | 所属学科 |
| 焼津市 | 障害者福祉のPRと人材確保 | 楢木 博之 | 福祉心理学科 |
今年度は、障がい福祉で働く専門職の仕事の魅力を知ってもらうために、インタビューを行いました。障がい福祉の専門職は、働いてからキャリアアップできる職業になります。障がい福祉の現場で働く人がどのようにキャリアアップをしているかの背景及び方法、プラスになったことなどを聞きましたので、紹介します。
インタビュー1
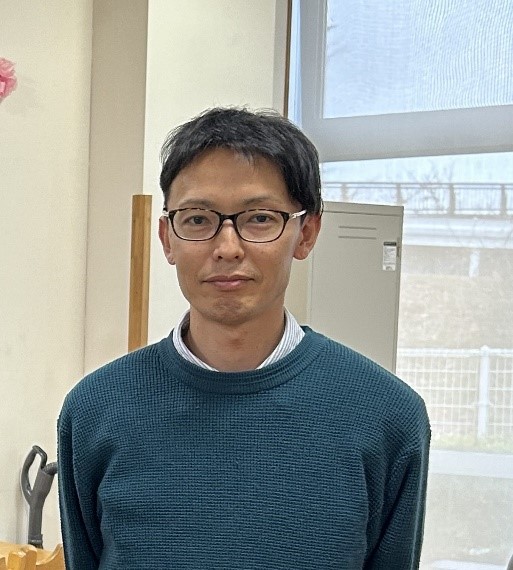
虹の家 サービス管理責任者 片岡信明氏
Q1.この仕事を選んだきっかけは?
学生時代に、軽度の知的障がいを持った方と少し関わりがあり、それをきっかけに興味を持つようになりました。焼津市に知的障がい者の施設があることを知り、受けてみようという気持ちになり、ご縁をいただき焼津福祉会で働くことになりました。
Q2.どのようにキャリアを積んできたか?
Q3.キャリアアップを考えるようになった理由は?
Q4.キャリアアップをしたことで自己のプラスになったことは?
サビ管は、地域の機関、社会資源を理解し、関わり(繋がり、パイプ)を大切にしなければなりません。そうして日々仕事をこなしていく中で、支援の引き出しが増え、視野もそれなりに広くなったと思います。このような点もプラスになったと思います。
Q5.障がい福祉の仕事の魅力は?
また、“その方の人生に関わらせてもらっている”という部分ですかね。折角、関わらせてもらっているので、私だったらやはり楽しんでもらいたいと思っています。一人の方の人生に携われるというのは、すごく魅力的だと思います。人と人との関わりは、毎日同じではなく、その日の機嫌、調子もあり、それによってこちらも関わり方を変えていかなければならないし、こちらの関わり方で相手にも変化があります。日々変化のある人間同士の関わりが魅力であり、私の楽しみでもあります。
Q6.福祉職を目指す人へのメッセージをお願いします。
なかなか学生のうちに自分のキャリアプラン、理想像を思い描くことができない人もいると思います。それでも私のように、まったく福祉と関係ないところから飛び込んできても自分の考え方や、やり方次第でキャリアアップできる職業だと思いますし、キャリアアップできる環境が整っている職業だと思うので、どんどん福祉の仕事に飛び込んで来てもらいたいです。


インタビュー2
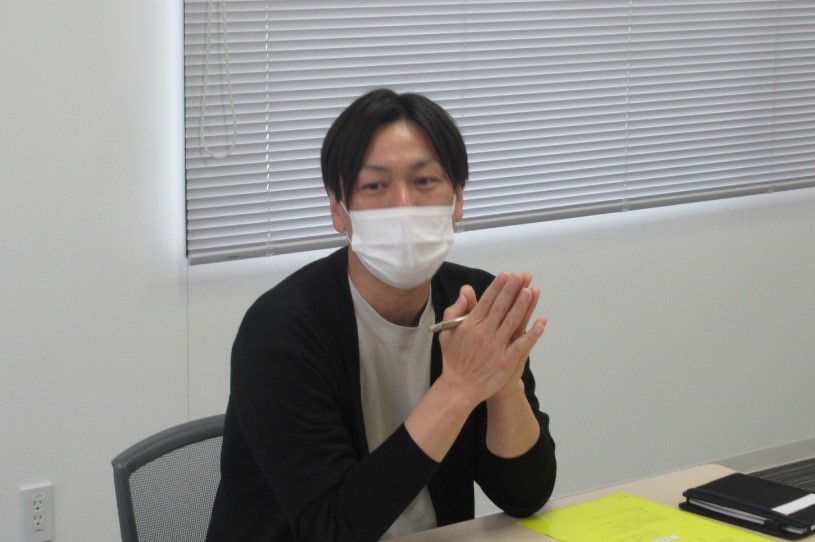
大井川寮サービス管理責任者 西井雄也氏
Q1.この仕事を選んだきっかけは?
Q2.どのようにキャリアを積んできたか?
Q3.キャリアアップを考えるようになった理由は?
Q4.キャリアアップをしたことで自己のプラスになったことは?
Q5.障がい福祉の仕事の魅力は?
Q6.福祉職を目指す人へのメッセージをお願いします。


インタビュー3
焼津市基幹相談支援センターCOCO 富永直樹氏
Q1.福祉の仕事に就いて良かったことは?
Q2.働きながら社会福祉士・精神保健福祉士を取得した理由は?
精神保健福祉士は、入社7年目に法人からの出向で東京都にある全国社会福祉協議会へ行きました。そこで、精神障害者の方の精神科への長期入院の問題があるというのを初めて知りました。精神障害者の置かれている現状を初めて知ったことが、勉強しようと思ったきっかけです。
Q3.現在の仕事の魅力は?
Q4.障がい福祉の仕事を続ける上での原動力は?
また、ご利用者本人のライフステージによって、関係するチームが変化するというのもあります。例えば、子供の頃であれば、子供に関係する幼稚園や事業所がチームになっていきます。 それが、大人になってくると、成人の施設や多機関との関わりも増えてきます。このように変化が起こってくるのが目に見てわかるし、関係する機関が多くあるので、チームで一緒に考える視点がすごく大事になってきます。個人の変化がチームの変化を生み出すし、チームの変化が社会の変化を生み出すみたいな感じのところが障がい福祉ではあると思います。そこはすごく魅力的かなと感じていて、この仕事を続ける原動力になっています。
Q5.現在の仕事で意識していることは?
Q6.福祉職を目指す人へのメッセージをお願いします。
インタビュー4
インフィニティJOBスタイル 近江なほみ氏
Q1.現在の仕事に就いた経緯
実は全く福祉のこともよく分かっていなくて始めたということもあるので、皆さんよりも知識がない状態から始めて、ただただ何とか障害のある皆さんが生きやすい世の中になってほしい。
彼らのことを受け入れてくれる人が1人でも多くなってほしい。そして「一緒にお仕事をしよう」と思ってくれる人が1人でも、それから一企業でも増えてもらいたいなということを思いながら、私たちに何かできることはないかなということで始めたのが経緯になります。
Q2.働きながら資格を取得した理由
働きながら保育士を取るというのは実はかなり大変でした。その時は必要性があるなと思ったのですが、ちょっと意地もありました。私だって保育士取れる。本当にそういう気持ちがあって、子どもたちのために何かしたいよという意欲、気持ちがあれば取得は可能だということを職員にも見てもらいたかったとこともあって。最初に私がやるべきだなと思って資格を取得したということです。
Q3.キャリアアップをしたことで、自分のプラスになったこと
それから障害のある方たちの理解を社会に広めるという意義が、話をすることで多くの人たちにそれを知ってもらうことができるのです。例えば会社の社長にそのことを知ってもらうと、すごく波及が大きいので。自分の従業員、それからその社長の人脈にまた働き掛けてくれるので、理解がすごく深まっていくのではないかなと思っています。
キャリアアップして自分にプラスになったのは、大切な人脈、人とのつながりが得られたということが、一番だと思います。
Q4.キャリアアップをする上で、必要なことは?
私たち職員が大切にしているのは「傾聴」です。まずは相手の話をしっかりと聴く。否定をせずにまずは聴いてみる。それで自分の考え、思いと少しすり合わせてみる。それで自分の感情がいろいろなことが湧いてくると思うのですよね。それをきちんとした日本語で適切な声のトーンや、適切な表情で相手に伝える。相手に受け入れてもらえるような話の仕方で言うということ、すごくテクニックがいるのです。この人がすごく人がいいからこういうことができるのだよというのではなくて、実は生きていくためのテクニックになります。
Q5.キャリアアップを考えた理由は?
私はペアレントトレーニングというものも受けています。放課後等デイサービスは子育てをするお父さんお母さんに対しても、子育てのサポートをするというのが大切な仕事の一つです。子どもたちを見ていくに当たって、子どもの家の環境を無視してはできない状態になります。必ず、子どもたちの背景にはどういった所に住んでいて、どんな親御さんで、どのように暮らしているかということが、はっきりと前に見えてくるのです。だからこそ親御さんたちに、「こういう時にはこんな声掛けをしてみたらいいかもしれない」などと、視点の切り替えを促すというのがペアレントトレーニングの内容になっています。このようなことができるように、学び続けています。
Q6.福祉職を目指す人へのメッセージをお願いします。
障がいのある人たち、それから介護も同じだと思いますが、やはり人は人でしか癒やせないと思うし、人が人でしかサポートできないことが多くあると思います。なかなか大学を卒業しても、福祉職にそのまま行くことに躊躇することもあると思いますが、私たちは皆さんが福祉業になっていくことを、企業の人間からしてもとても望んでいます。今後なくならないこの仕事を、未来に期待しながら、ぜひ就職してもらえたらなと思っています。